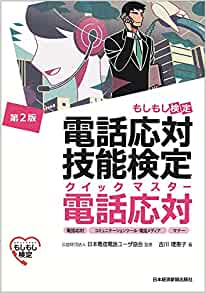不要不急の外出を控え、自宅にこもることの多い毎日を過ごしております。
不要不急の外出を控え、自宅にこもることの多い毎日を過ごしております。
比較的早い夜の時間、最近はオンデマンドによる昭和の名作アニメを観ています。
「巨人の星」、おそらく40代以上の方なら、タイトルくらいは聞いたことはあるのではないでしょうか。
1968年から1979年にかけて放送されたTVアニメで、プロ野球巨人軍を目指して猛特訓に励む父と息子の、そして後半は巨人軍に入った息子の、スポーツ根性ものです。
楽しむポイントはいろいろとあるのですが、今回は対人処世術の観点から、「あ~、なるほど。」と思い当たったことについて、書いてみることにします。
他人が自分に対してする”嫌な言動”の意味は?
「巨人の星」第35話「魔球対剛速球」の中に、考えさせられるシーンがありました。
主人公の星飛雄馬(ほしひゅうま)は、16歳。
甲子園初出場の青雲高校の投手です。
左の本格派、剛速球投手で、幼いころから父にしごかれて、針の穴を通すコントロールと根性、野球理論を持ち合わせています。
対戦相手は、前年度優勝校の三河高校。
エースの太刀川(18歳)は、きれの良いドロップを決め球にする変化球投手です。
今風に言えば、縦におちるカーブでしょうか。
息詰まる投手戦が続き、太刀川は17奪三振です。
0対0、9回裏二死、打者は太刀川の場面でのこと。
太刀川は、バントをします。
飛雄馬は、軽快なフィールドワークで簡単に処理をします。
そこで、「?」となるのです。
「俺の投手守備が下手でないことを、太刀川は知っていたはずだ。
なのにどうして、バントをしたんだ。」
そこで、ひらめくのです。
17奪三振、ここまで投げてきた太刀川は、疲れている。
バントで右に左に揺さぶられては、足がついてゆかないと恐れた。
そして彼は思った。
「自分が苦しい時は、相手も苦しい。」
だから飛雄馬が嫌がるだろうバントを、彼はしたのだと。
飛雄馬は、体力温存しながら投げていたので、太刀川ほど疲れてはいませんでした。
だからそのバントを処理できたのですが、この不自然なバントで太刀川の疲れを飛雄馬は見抜くという筋です。
これを見て、なるほどと思いました。
いつも他人に嫌なことを言う人、たぶん嫌がるだろうことを探している人、誰の身の周りにも少なからずいることと思います。
たとえば学歴、たとえば運動神経、スポーツの成績、家庭環境、容姿、所属している会社や団体等々。
こういうことを会話の中に織り交ぜて、相手の顔色をうかがい、相手の弱いポイントを探っているような人。
この人たちのついてくるポイントは、実は本人が弱いところなのです。
自分がそれを弱みに思っているから、相手もきっとそうだろうと思うのです。
それならば、その挑発にのるのは愚の骨頂です。
自分から自分の弱みを見せてくれているのですから、
「ああ、この人はこういうことに、コンプレックスがあるのね。」
と認識して、その次の言葉を選びます。
もしぴしゃりとやりたい(やっても良い相手なら)のなら、そのように。
うけながさなければならない相手であれば、むしろにっこり笑って受け流す。
巨人の星を見て処世術を学ぼうとは思いませんでしたが、さすが昭和の名作アニメ、なかなか深いです。
外出自粛はまだまだ続きそうですから、昭和の名作を楽しむ時間はたっぷりあります。
面白い気づきがあれば、またここで報告させていただきます。

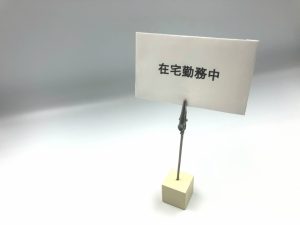
 年度が変わり、令和2年度が始まりました。
年度が変わり、令和2年度が始まりました。